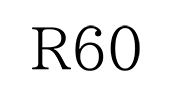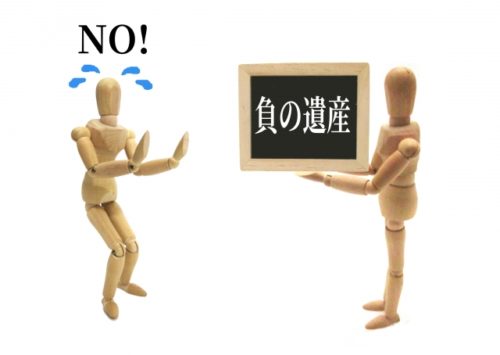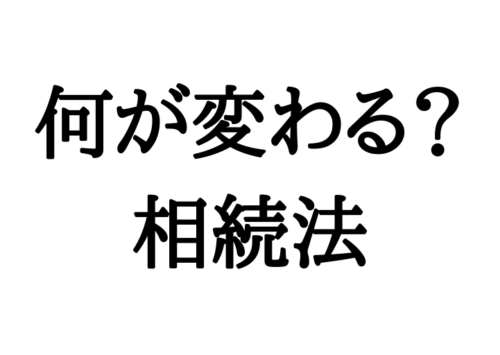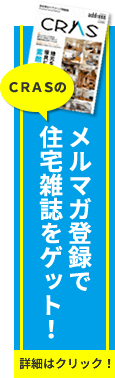生命保険(死亡保険)を活用して、相続税を節税する方法があることをご存知でしょうか?
生命保険には非課税枠というものが設けられており、その枠の範囲内であれば相続税がかかりません。
このような制度を上手く利用すれば、収める相続税の額を少なくすることができます。
相続において生命保険はどのような扱いになる?
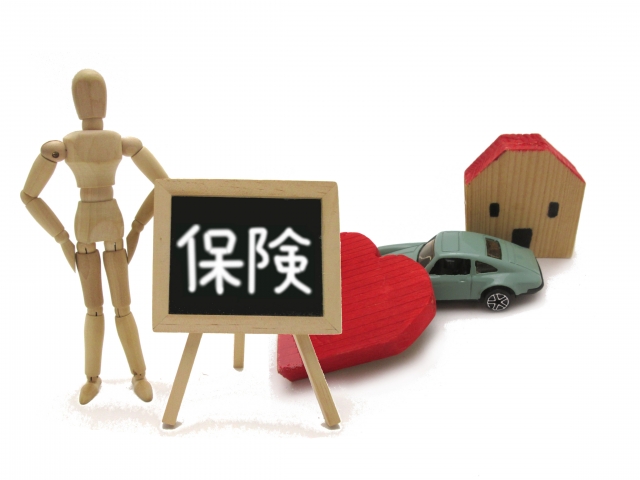
以前にもお話ししましたが、生命保険は相続においてみなし相続財産となります。
生命保険は亡くなった方が保有していた財産ではありません。
亡くなったことで発生する財産となります。
しかし、実質的には相続で獲得した財産とみなされ、「死亡退職金」などと同じようにみなし相続財産として扱われます。
また、生命保険が相続税として扱われるためには、契約者と被保険者が被相続人(亡くなった方)で受取人は相続人でなければなりません。
そうでない場合は、税の種類が変わることとなるので、この点においては気をつけておきましょう。
生命保険には非課税枠がある

生命保険には非課税枠というものが設けられています。
非課税枠の計算方法を以下のようになります。
500万円×法定相続人の数
法定相続人の数が4人であれば、500万円×4人で2,000万円まで相続税がかからないこととなります。
では、保険料の負担者がAさん、被保険者がAさん、保険金の受取人がBさん、保険金の受取額が800万円で、保険金以外の相続財産が5,000万円ある場合の相続税の計算の仕方はどのようになるのでしょうか?
相続人はBさんの1人だけとなるので、保険金の非課税枠は500万円です。
そのため、保険金の受取額800万円から500万円を引いた300万円に対して、相続税が課税されることとなります。
保険金以外の相続財産が5,000万円あるので、課税される保険金の300万円を加えると、課税される財産の合計額は5,300万円となります。
次に、課税される財産の合計額が5,300万円から基礎控除を引きます。
基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」なので、今回は3,600万円となります。
課税される財産の合計額が5,300万円から基礎控除の3,600万円を引くと、課税相続財産は1,700万円です。
相続税の税率を用いて計算すると、納税額は1,700万円×15%-50万円=205万円となります。
生命保険を上手く活用することで節税できる

生命保険は相続前の現金や預金を減らす効果もあるので、相続財産が少なくなる場合もあります。
相続財産が少なくなると必然的に課税額が減ります。
また、非課税枠が設けられているので、上手に活用すると多くの金額を節税することが可能です。
このような制度を上手に使って、納める税金の額をなるべく減らしたいものですね。